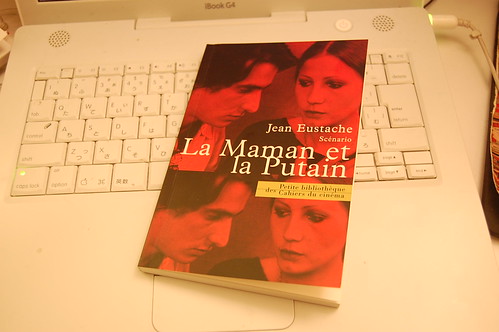アンスティテュ・フランセにて。ルイ・ガレルが監督した44分の映画「小さな仕立屋」堪能。フィリップ・ガレルの息子の、彫刻みたいに美しい彼。噂の若手女優レア・セドゥが出てる。この2人は「美しいひと」で共演してた。今回は監督と女優という関係。小さな仕立屋で跡継ぎとして期待される若い男が、若い女と出会い、恋に耽るが故に仕立屋仕事といつしか天秤にかけ・・という物語。
モノクロで捉えられた2010年のパリは現代か過去なのか一目ではわかりにくい。去年の秋、恵比寿の写真美術館の前にあるドアノー「市庁舎前のキス」を指さして、一緒にいた人と「この写真が好き」と意見は一致したのだけど、その人が好きな理由を「瞬間瞬間が、一回性のものだと思い知らされる。永遠に戻らない瞬間の儚さが捉えられた写真」と言ったのを、ふうん。って聞きつつ、でもパリってこれだけ前の写真でも全然変わらないし、こういう感じで市庁舎前でキスしてるカップルっていつでもいるし、これが現代に撮られたって言われても驚かないけどな。って心の中で思ったことを思い出した。私にとってのモノクロのパリはそれ自体が永遠をはらんでるのかもね。2010年ルイ・ガレルの撮ったパリはヌーヴェルヴァーグにも通じるし、それ以前の映画にも通じるのかもしれない。
レア・セドゥ演じる蠱惑的な女を前にして、仕立屋はいかにも不器用に見えた。反射的にトリュフォーの「柔らかい肌」を思い出す。飛行機で乗客とスチュワーデスという間柄で知り合い不倫の恋に落ちる男女の物語だったが、男の細かい行動がいちいち鈍臭く、不倫を狡猾にやり過ごせるように見えない・・と思っていたら悲惨な結末が待っているのだ。例えば冒頭、離陸が近づき、男は煙草を消すように言われるのだが、すぐには消さず、しぶとく吸っている。注意されてすぐ消すような男であれば、不倫もきっとうまくやり過ごすのではないか。例えば街中でのデートの場面。踊る女の可愛さに、男はその先を期待してホテルを探すため店にある電話帳をにやけた顔でめくる。男が選んだのは人目を避けるような場末の安ホテル。うらぶれた場所に煌めいたフランソワーズ・ドルレアックはいかにも不似合いである。あの場面であんなホテルを選ばない男であれば、不倫もきっとうまくやり過ごすのではないか。
小さな仕立屋は、女が寝ている間に身体のサイズを測り、彼女にぴったりのドレスを仕立て上げる。しかし、そのドレスがオリジナルではなくコピーなのはいただけない。それがコピーであると女に打ち明けるのはさらにいただけない。メトロが苦手でいつもパリじゅうを走っているが、ここぞという急ぎの場面で、その流儀を変えられないのもいただけない。多くのヌーヴェルヴァーグの映画の結末のように、ほろ苦さが残るあたりも、ルイ・ガレルはヌーヴェルヴァーグの正当な末裔であることを証明する44分。
それにしてもレア・セドゥの美しさ。PRADAの映像が話題になってるけど、モードを着てニコニコするレア・セドゥは本領発揮していないように思える。「美しいひと」以来、レア・セドゥのレア・セドゥらしさをふんだんに引き出したルイ・ガレルはきっと、女を見る目があるのだろう。