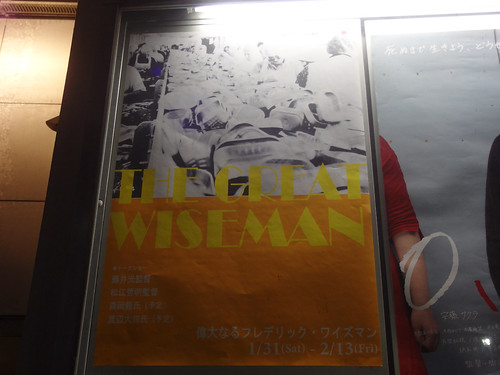ゴダール新作も始まった東京、観るつもりだけど、フレデリック・ワイズマン特集、2週間で終わってしまうので優先順位はこちら。長い映画が多いので最終上映開始時間が早く、仕事帰りに観に行けない。そして休みの日に時間が合いそうなのが「ドメスティック・ヴァイオレンス」だったりして、ここのところTVをつけるだけでニュース映像に気持ちが疲れてしまう日々が続いていたので、どうにも観る元気が出ない。
数行の映画説明を読み、比較的大丈夫そうなのを慎重に選ぶ。1983年のドキュメンタリー「ストア」は、82年、クリスマスシーズンの百貨店を撮ったもの。舞台はニーマン・マーカス本店。本店ってダラスにあるのね。百貨店で働く人々や、バックヤード、買い物客が映されている。
セールスミーティングでのお偉方の言葉。百貨店の存在意義は「物を売る」ことにある。当たり前なのだけど、言葉がクリアで無駄がない。婦人服売り場の販売員朝礼のような場所では、フロアリーダーなのか、女性が前に立ち、私たちの仕事に必要なのは、笑顔と手である!と力説し、だから柔らかくしておきましょう。と、首回りほぐしたり、手をぶらぶらさせたり。手が大事なのは、レジ打ちをするから、らしい。
毛皮売り場の上顧客担当は男性で、特別室のような別室で、奥さんに買うのか、男性相手の接客。カーペット敷きとはいえ、毛皮の裾が床についてもどちらも気にするそぶりもないのに驚き。お国柄…?なぜ床につかないように持ち上げない…?4万ドルもするのに…。
ニーマン・マーカスは老舗高級百貨店で、接客される顧客もどこか浮世離れしたような富裕層が多い。特に老婦人は、実業家の妻という感じの人ばかり。でも接客は慇懃な感じはせず、言いたいことは率直に言う。ドキュメンタリーを通じて、一切、説明がないので想像するしかないのだけど、担当してもらって20年、彼女からしか洋服は買わないの。というような、長年の信頼関係があるのかしら。従業員のほうも、顧客の生活や交友関係、クローゼットの中身まで把握した上でアドバイスしてるようだった。
この写真の場合、花柄のスカートを老婦人は気に入っているのだけど、腰に手をやる従業員は反対で、確かにいいスカートだけど、布地たっぷりで重いから、パーティーで長い時間履くと身体に堪えるのではないか?と主張して両者譲らず、の場面。
これは従業員休憩室のような場所で、50代に見える女性従業員の誕生日のサプライズお祝い。着ぐるみに入ってるのはたぶん中年男性で、ところどころ卑猥な言葉を浴びせつつ、最後にはストリップみたいに脱ぎ始めた…。今これやるとなんとかハラスメントでややこしい問題になりそう。80年代、おおらかな時代だったのね…。
宝石の接客の場面の次に、バックヤードで指輪の絵を描く人が映し出されたから、宝石売場の販促用の何かを描いてるのかな?と思ったら、デザイン画だったようで、道具を駆使してジュエリーを製作してる様子が映される。バックヤードものでは他に、洋服の縫製の場面があって、パンツの裾あげなどをするお直しセンターかな?と思ったけど、それ以上の本気度で、デザインから縫製まで一気通貫で洋服を仕立てる場所のようだった。ニーマン・マーカス、オリジナルでジュエリーや洋服を作ってる(作ってた?)のだろうか。不思議。あんなバックヤードのような場所で…。
それから面白かったのは、採用面接の場面。話を聞く限り学生(なのだけど、とても学生に見えない落ち着き)の女性が面接を受け、採用担当なのか男性が質問を投げかける。インターンで販売の仕事をして、特定の売り場だけでなくあらゆる売り場を担当し、その度に商品の特徴を覚えるのが楽しかった…などとアピール。通り一遍の質疑応答の後、最後にひとこと言いたいことありますか?と言われてからの、学生のアピールの長いこと長いこと。ニーマン・マーカスは憧れの場所であり、私はその場所にふさわしい人間になれるようたゆまぬ努力を続け、ついに今日、そのような人間になったのである。ですからして、募集されているこのポジションには、私の他にふさわしい人間はいないのである。もちろんこんな口調ではないけど、言いたいことはこんな感じ。
語学を勉強していると、教材に面接のシチュエーションでその言語を学ぶチャプターがよくあって、他の当たり障りない会話より、お国柄が出るなぁ。と思う。中国語で読んだのは「就職活動大変ですね」「そうですね、あなたコネありますか」「私はあります」「それはいいですね。私はないから大変です」という学生らしい初々しさ皆無の会話。コネ、中国語で「門路」って単語なのをその時知った。フランス語では、就職面接に来た中年女性と面接官の会話で、あなたなぜ仕事探してるんですか?と聞かれた中年女性が「これまで夫の会社で働いてたんだけど…夫が秘書といい感じになって…あの…ねえ…わかるでしょ?」という受け答えで、さすがに先生も「この人は自分のことを話し過ぎてるわ!」と呆れ顔だったけど、私はありがちなフランス映画か!とツッコミ入れた…。
そしてニーマン・マーカスの面接。従業員たちの様子を見ていても、人前でいかに魅力的な自分として堂々と話せるかが、ひとつの教養として重視されるのだなあ。最後に採用担当者が、面接はこれで終わりで、結果が出るまで3週間。それまでの間、あなたの前の勤務先や家族状況など、まわりの人に身上調査をさせてもらうよ。と本人の前で言ったのにも驚いた。高級百貨店だから経歴や育ちを気にするのだろうけど、そういうのは秘密裡に進めるものではないのだろうか。本人も驚いた様子もなかったから、当然のこととして受け止めているのだろうな。
ダラスの人々に、ニーマン・マーカスが拠り所のような場所であることは確かなようで、バイヤーは小さな頃の特別な思い出といえば、ニーマン・マーカスのレストラン(星座レストラン、と言っていたように思うのだけど、どんなレストランなのだろう)で食事したことか、ケネディ暗殺か、ダラスっ子ならそのどちらかね!と話しており、おお、ダラスってそういう場所なのだな、と妙に感心。
フレデリック・ワイズマンのドキュメンタリー、視点をここに置け。と映像に指示されないので、視点はどこにでも好きに置いて良い。観る人の数だけ印象は違うだろう。消費社会に警鐘を鳴らすためにワイズマンはこれを撮ったのだ!と主張する人もいるだろうけど、そのような感想の人はきっと、消費社会に警鐘を鳴らしたい欲望がある人なのだろうと思う。私はただ、ちょっと深くまで入って82年のアメリカを定点観測した映像に思えた。スタッズ・ターケルがアメリカのあらゆる職業の人にインタビューして本に記録した切り口の映像版のような。公開当時に観ても面白くないかもしれず、30年以上経った今観ると、インターネットもない時代、人々は高級品を買おうとすると、ニーマン・マーカスで従業員に相談しながら買う。従業員はそのために準備をする。という、買い物の原風景のように見えて、もはや懐かしい。従業員たちのミーティング風景にもPCや携帯電話は登場せず、販売方針を伝えるのも何もかも、人から人へ。というシンプルさ。現在はそれに比べて販路は増えたけど、ミーティングで話される内容を聞いていると、販路が増えただけで販売戦略のようなものは30年前からたいして変わっていない。物を売ることはきっと人類誕生の初期からあるはずの職業で、本質はたいして変わってないんだろうな。という視点から、私は観た。
最後は創業75周年を祝うセレモニーで、会長が「マイ・ウェイ」を歌う場面で終わる。2時間、百貨店を映すだけの映像なんて退屈するかな。と思ったけど、まったく退屈せず、加速度的に面白くなる独特の体験。叙情を廃した淡々とした撮影、ところどころ挿し込まれるエスカレーターのショット、百貨店という巨大な生命体の大動脈のようで、クールで痺れた。